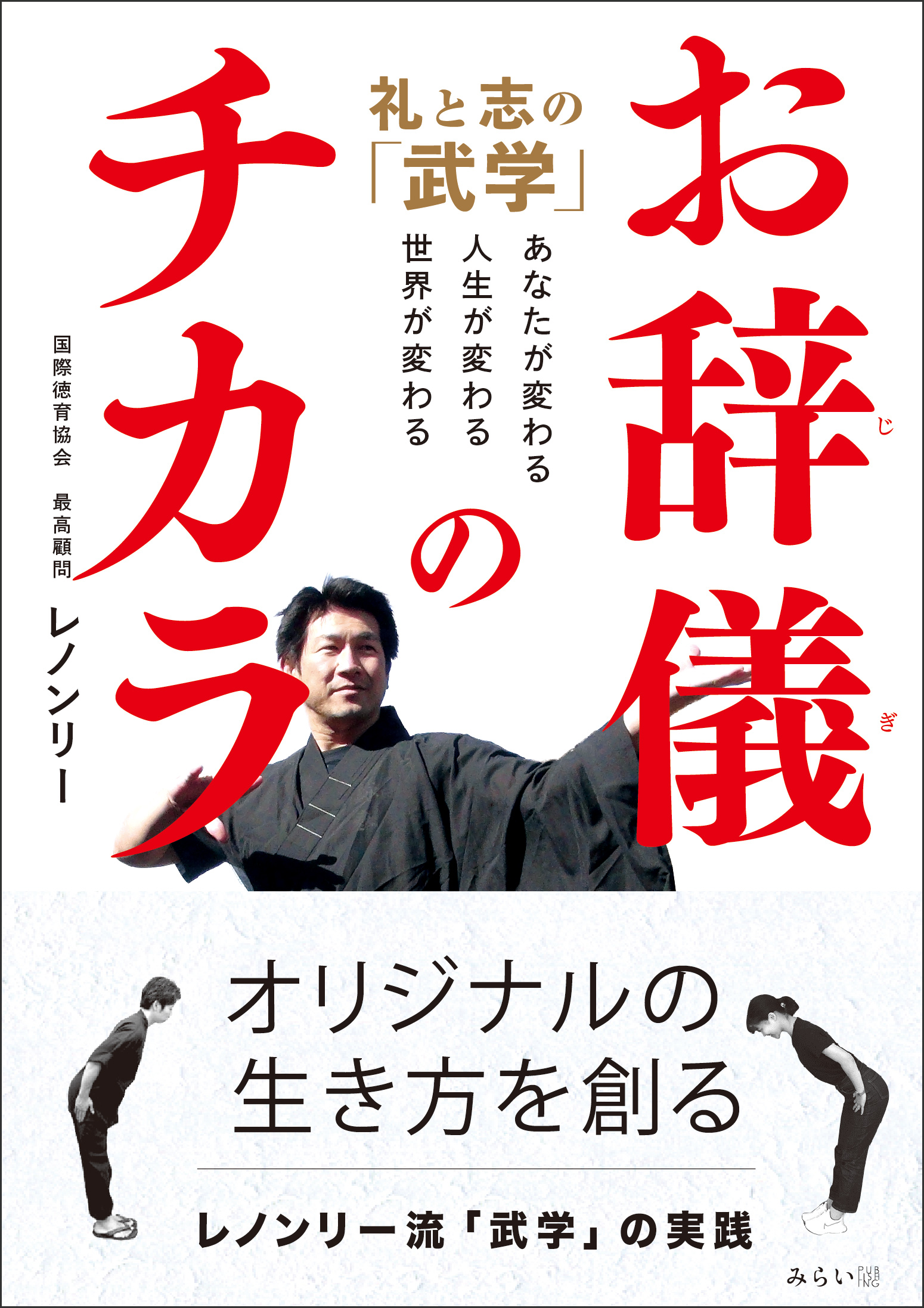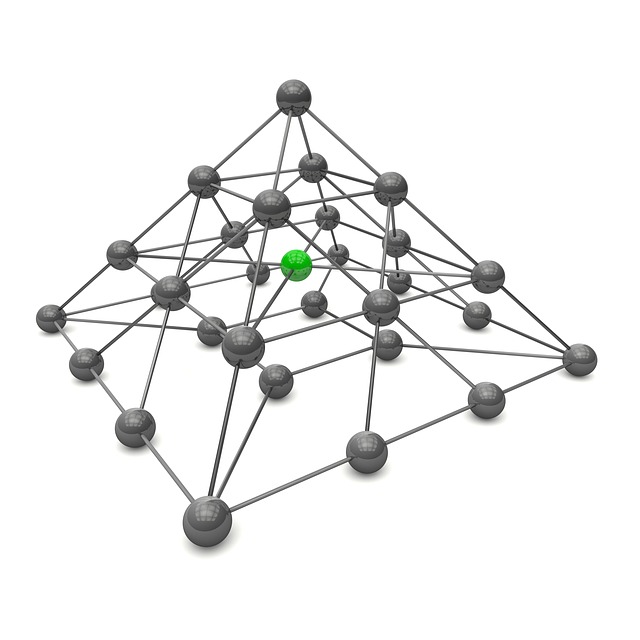今回は、モノの観方(見方)について(前編)として、お伝えしていきます。
まず題名を見て(観て?)「はてな?」と思った方もいらっしゃると思いますので、漢字の「みる」についてお伝えします。
「みる」は5種類
あります。
「見る」「視る」「観る」「診る」「看る」
です。
この順番に「深く」なっていきます。
その理由は、漢字から出来上がる「単語」でわかります。
これからお伝えする意味は、オリジナルですので、学校のテストで意味を書いても点数はもらえないかもしれません。
「見る」:見物など
→そこにあるものを目に止めること
「視る」:視線など
→全体を視野に入れること
「観る」:観賞など
→それが何なのかを観察すること
「診る」:診断など
→観た結果、何なのかを判断すること
「看る」:看護など
→診た結果、対応(ケア)すること
なので、お医者さんが短時間で診断するのは、「診る」とは言わないかもしれませんね・・・
さて・・・これらの「みる」ですが、実は
「バイアス」がかかっています
「解釈」が入る
とも言えます。
次の図を使って、お伝えしていきましょう。
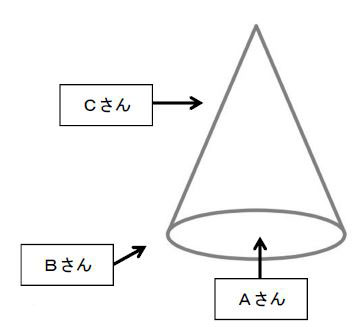
円錐形があるとします。
Aさん・Bさん・Cさん、それぞれの人が矢印の方向から見ています。
Aさんは「丸」
Bさんは「扇型」
Cさんは「三角」
に見えます。
「これは丸である」
「いやいや扇型だって」
「はあ?三角以外のなにものでもない」
こうしたことが日常では起こっているのです。
「どちらが正しいか?」
のぶつかり合いが起こっているのであり、
一部分を切り取って反射的に湧き起こる「感情」=「心」に振り回されている状態です。
もしも一部を切り取って「みて」いることを認識しているとしたら、相手の見る位置に行くことも、自分の見る位置に来てもらうこともできるようになります。
また、俯瞰することができたら、どうなるでしょうか?
「離れてみる」ということです。
「なーんだ、みんな違う角度でみていただけやんけー」
となりませんか?
円錐の一部分を切り取って「みる」だけではなく、多くの視点から「みて」、全体としての形をみようとする。
つまり、
本質とは何か?
を見落とさないようにすることが大切になります。
武学の中で、
■生まれ持った癖を取り除いたときに原理原則に戻る
■こだわるとこだわらないがわかる
■1つ終わったら、こだわりを捨てる
というものがあります。
どんな「みかた」の癖を持っているのか?を知ることで、初めて「手放す」ことができるようになるのです。
今回の動画は、約3分20秒です。
少し違う視点の「武学での身につけるとは」でお伝えしています。

武学三軸「志×禮×行動」をバランス良く整えることで、誰もが自分の可能性に氣づき、持てる力を存分に発揮し、多くの人や社会に貢献する事ができる「武学舎」を作りました。
「武学舎」を無料で体験できる「無料開門コミュニティ」にご参加いただけます。